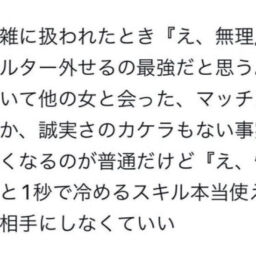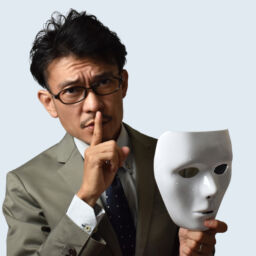皆さん、こんにちは。
今回のコラムでは、夫婦の間で起こりうる、非常にデリケートな問題について考えていきたいと思います。
それは、もしあなたのパートナーが、回復の見込みの薄い重い精神疾患を抱えてしまった場合、ということです。
人生には、予期せぬ困難が訪れることがあります。
特に、共に人生を歩むと誓ったパートナーが病に倒れてしまうことは、当事者の方だけでなく、その周りの人々にとっても大きな試練となります。
愛情や責任感から、懸命に支えようと努力されるのは当然のことでしょう。
しかし、終わりが見えない介護生活の中で、心身ともに疲弊し、将来に希望を見出すことが難しくなってしまうこともあるかもしれません。
実際、このような状況に置かれた方が、離婚という選択肢を考えることは、決して珍しいことではありません。
法律も、婚姻関係がもはや耐えがたい拘束となってしまった場合には、一定の範囲で離婚を認めています。
ここでいう「精神疾患」とは、非常に広い範囲を指します。
例えば、私たちの身近にも起こりうる、うつ病や不安神経症、適応障害、記憶障害、アルコール依存症なども含まれます。
しかし、民法770条が定める離婚原因の一つである「配偶者が強度の精神病に罹り、回復の見込みがないとき」というのは、より限定的な疾患を指しています。
具体的には、統合失調症、認知症、双極性障害、そして妄想性パーソナリティ障害などが挙げられます。
では、これらの疾患は具体的にどのようなものなのでしょうか。一つずつ見ていきましょう。
統合失調症
統合失調症は、以前は精神分裂病と呼ばれていた病気です。
決して珍しい病気ではなく、人口の約1%の方が発症すると言われています。
思考がまとまりにくくなることから始まり、現実にはないことを信じ込む誇大妄想や被害妄想、誰かに追われていると感じる追跡妄想といった陽性症状が現れることがあります。
一方で、感情が乏しくなったり、他人との関わりを避けたりする陰性症状も見られます。
認知症
認知症は、高齢になるにつれて発症する可能性が高くなる病気です。
会話がうまく成り立たなくなったり、数分前のことを思い出せなくなったりする記憶障害に加え、妄想や徘徊、暴言、さらには異食といって、食べ物ではないものを口にしてしまうといった症状が現れることもあります。
残念ながら、現在の医学では有効な治療法や特効薬が見つかっておらず、介護に疲れたご家族による家庭崩壊が社会問題となっています。
双極性障害
双極性障害は、一般的に躁うつ病とも呼ばれています。
極端に気分が高揚し、何でもできるような万能感に包まれたり、眠らなくても平気になったりする躁状態と、反対に、将来に対して悲観的になったり、何もかもがつまらなく感じたりするうつ状態を繰り返すのが特徴です。
他の精神疾患と合併して症状が現れることも少なくありません。
境界性人格障害(自己愛性、妄想性など)
境界性人格障害の中でも、特に配偶者との関係において問題となりやすいのが、自己愛性や妄想性の特徴を持つ場合です。
根拠のない猜疑心を抱き、例えば「浮気をしているのではないか」「昔の恋人とまだ会っているのではないか」といった疑念に固執し、相手を激しく攻撃することがあります。
さて、これらの「強度の精神病」に該当する病気であっても、法律は安易な離婚を認めていません。
配偶者を見捨てるような形での離婚は、原則として認められないのです。
しかし、人間には忍耐の限界があります。
特に、相手が共依存的な人格障害を抱えている場合、その望むままに傍に居続けることが、相手の依存をさらに深めてしまうことがあります。
最悪の場合、共倒れのような形で、二人とも抜け出せなくなってしまう可能性さえあります。
このような状況で離婚の判決を得るためには、いくつかの重要な要素を考慮し、主張していく必要があります。
まず、パートナーの病状が重く、もはや回復の見込みがないと医学的に判断されることが重要です。
医師の診断書などが有力な証拠となります。
次に、婚姻関係を継続することが、あなたにとって耐えがたい苦痛や拘束にしかならないという状況を具体的に示す必要があります。
長期間にわたる介護の苦労や、精神的な負担などを具体的に伝えましょう。
また、これまであなたが長年にわたり、献身的に介護をしてきたという事実も、裁判官の判断に影響を与える可能性があります。
そして、離婚後のあなたの生活や、病気のパートナーの治療や生活について、ある程度の見通しを立てていることも重要です。
例えば、経済的な自立の計画や、パートナーの今後の療養体制などを具体的に説明する必要があります。
これらの理由を、事実や証拠に基づいて丁寧に訴えかけていくことが、離婚への道を開くために不可欠となります。
ここで、少し具体的な事例を考えてみましょう。
最近、SNSを中心に注目を集める某インフルエンサーの方が、薬物中毒から薬物性統合失調症を発症しているのではないかという情報が上がっていました。
SNSから垣間見えるその精神状態は非常に不安定で、周囲の人間関係にも大きな影響を与えているようです。
報道によれば、身の危険を感じたご家族が彼の元から逃げ出したにもかかわらず、彼は依然として家族への依存執着を示しています。
止まらない暴言や見境のない行動によって、家族を深く傷つけ続けているとのことです。
さらに彼は、自身の精神的な不安定な様子を、ほぼ24時間眠らずにSNSで公開しています。
それによって得られる承認欲求が、更なる妄想や不安を引き起こしているのでしょう。
その苦しみから逃れるために薬物依存を続けてしまうという悪循環に陥っている可能性も指摘されています。
もしこの事例が事実であれば、逃げ出した妻は、夫の「精神障害」を理由に離婚を争うことも十分に可能でしょう。
夫の病状の重さ、回復の見込みの薄さ、そして何よりも、妻が受けた精神的な苦痛は計り知れません。
もちろん、このような状況は非常に特殊なケースであり、一般の夫婦関係とは異なります。
しかし、この事例は、重度の精神疾患が、夫婦関係に深刻な影響を与える可能性を示唆していると言えるでしょう。
精神疾患を抱えるパートナーとの生活は、想像を絶する困難を伴うことがあります。
愛情や義務感だけでは乗り越えられない壁に直面することもあるでしょう。
そのような時、一人で悩まず、信頼できる人に相談したり、専門家の助けを借りることも大切です。
今回のコラムが、もし今、同じような悩みを抱えている方にとって、少しでも考えるきっかけになれば幸いです。
困難な状況ではありますが、ご自身の心身の健康を何よりも大切にしながら、最善の道を探っていくことを願っています。
最後までご視聴いただき、ありがとうございました。
もし、今日の話が少しでも心に残ったという方は、チャンネル登録と高評価をしていただけると嬉しいです。
また、コメント欄で皆さんの考えや経験を共有していただけると、大変励みになります。
それでは、また次回のコラムでお会いしましょう。